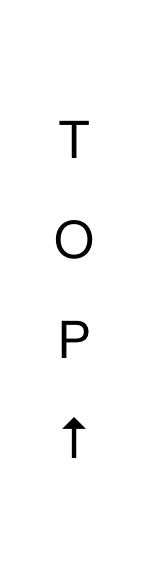Kesennuma

朝の魚市場は活気にあふれています。魚市場というと競り(せり)を思い浮かべる人も多いでしょうが、気仙沼市魚市場では<入札>で魚の取引が行われています。2025年4月現在、気仙沼市魚市場買受人は118社(令和7年4月現在 ※1)。今回の「海が教えてくれる」は、海産物出荷、小売、冷蔵倉庫、製氷、そして不動産業まで手がける足利本店の鮮冷魚出荷部の仕事に密着。営業本部長の小松新太さん、入社6年目の堀子翔平さんにお話しを伺いました。
■朝6時半、気仙沼魚市場
昨年(2025)5月に、気仙沼市産業部水産課 齋藤さんの案内で気仙沼市魚市場を訪れ、魚を買い付ける買受人さんが魚をチェックしている様子を遠巻きに見ていました。でも今回は、まさに現場仕事に密着です。
まずは、足利本店とは?ですが、天保11年(1840)に海産物の買い付けを生業に、次第に業務を拡大。昭和28年(1953)に会社を設立。海産物を消費者に届けるための鮮冷魚出荷部は、気仙沼以外にも塩釜や大船渡など各地で魚の買い付けを行っています。
魚市場に到着して車を降りると、すぐに見知らぬ車が私たちの車に横付け。すかさず小松さんが降りてきて、「朝のミーティングしてから、翔平を来させるのでちょっと待ってて」と慌ただしく去っていきました。ん、どこで見てたんだw
朝6時半過ぎ、ミューティングを終えた堀子翔平さんと合流。気仙沼市魚市場のC棟D棟は高度衛生管理対応のエリアなので、前回同様きちんと手洗い消毒し、市場内に入ります。そしてまずは、迫力満点のサメエリアへ。モウカザメ(地方名・毛鹿鮫、正式名称は鼠鮫)やヨシキリザメ、アオザメなど、種ごとに分けられています。

翔平 サメというとみなさんフカヒレを思い浮かべるけど、煮付けや唐揚げで食べる地域もあって、栃木県宇都宮市など北関東ではスーパーでモウカザメを売っています。文化として浸透してるんですよ。
育美 それは、知らなかった。関東でサメ?って思いますが、みなさんはお客さんの動向で、何が好まれているのかも分かるんですね。
翔平 仕入れの状況から、その食材がその地域で好まれているのか分かります、食材が地元でどのように扱われているのかも興味が湧きますね。
モウカザメを栃木県では「モロ」と呼び、農林水産省のサイト内でも栃木県の郷土料理「モロの煮付け」として紹介しています。

ヨシキリザメに並んで、大きなマンボウ?が……。実は体型はマンボウに似ているけど別の種で、アカマンボウと言います。神秘的な魚として話題になるリュウグウノツカイもアカマンボウ目に属しています。アカマンボウはハワイや沖縄で普通に食用にされていて、沖縄では「まんだい」と呼ばれているそうです。
サメのすぐ隣、翔平さんの担当であるマグロの場所に移動。買受人さんがそれぞれ、尾の断面を見たり、お腹の中を見たりと真剣な眼差しです。
育美 買受人さんって、どういうところを見て、買うかどうかを判断しているの?
翔平 身の硬さとエラの色で鮮度感を見ています。エラが赤いと鮮度がいい。古くなると茶色っぽくなってくるんです。

魚をチェックしながら、所定の入札用紙に書き込んでいく。魚の間を行き来し、魚を次々とチェック。
翔平 最初の半年間はずっと赤字でした。赤字だし、魚も買えない。他の人は100円以下でしか見ていないのに、僕が100円で入れたら当たっちゃった。値段と商品の質が合ってないから、「お前こんなもん売れるか!!」って怒られる。入札だから、人より高く買ったら素人でも当たる。でもそれって、ヘボいから当たるんですよ。
育美 状況判断しながら、すぐに自分で値段を決めて、それで入札できるかどう決まるって、覚えるまでが大変そう。低ければそもそも買えないし、高すぎてもダメだし……。

翔平 それでも買わなきゃいけないときもあるんです。お客さんに絶対買ってくれと言われ、先方が準備しているのに入札できずに欠品になったら、お客様の信用を失います。次から「もうお前のところには頼まねぇ」って言われてしまう。そのサジ加減、その場の判断は営業に任されています。上司に相談してというのはないですね。ほんと、個人商店みたいな感じです。
CD棟から沿岸の魚が集まるA棟へ。魚の大きさもグッと身近な大きさになります。見慣れた魚以外にも、水ダコ、アナゴ、サヨリ、太刀魚、伊勢エビなども……。「天然の水族館で楽しいでしょ」と翔平さん。ここで、小松さんも合流。

小松 お客さんも一人ひとり違います。少々悪くても安いものが欲しい、高くてもいいものが欲しいとか。いろんな性格のお客さんがいるので、一人ひとりのお客さんの性格を掴んでイメージしていて、先方の性格を知るのも重要です。
育美 小松さんのコミュニケーション能力もすごい! さっきも市場内でいろんな人に声をかけて、紹介してくれました。人の輪が広がっていく感じが素晴らしいです。
翔平 お客さんも、昔ながらの厳しい体型の先輩が多かったですよね。でも、仕事に対する考え方や優先順位を覚えることができたのは、そういう人たちのおかげかなとも思います。
育美 なんか人情というか、人と人とのつながりですね。会社の人はもちろんですけど、お客さまとのやりとりで覚えたという仕事も多いのでしょうね。
■魚を買うだけじゃない
気仙沼市魚市場で翔平くんが買った魚は、車で数分にある足利本店に運ばれます。ここから買った魚の処理に入ります。翔平さんも着替えて、処理作業に加わります。
翔平 仕入れ、魚の処理、原価計算までが私たちの仕事。お客さんに向き合ってるのは営業担当なので、担当者がお客さんの目線を合わせて、注文にあった商品を、現場で自分の目で見ないと深夜にクレームの電話が入ります。信用で取引できるような状態で今はやってるので、だからこそ現場に担当者が必要なんです。
育美 まさに解体するようにノコギリも使ってらっしゃいましたが、それぞれの部位の知識もないとできないですし、熟練の技ですね。お仕事の現場を拝見していて、みなさんがすごく生き生きと仕事をされてるし、仕事に誇りを持ってらっしゃるのかなっていう印象を受けました。
小松 年数を重ねたからってうまくなるわけでもないですし、センスも必要です。翔平は入社6年目ですけど、センスがあります。たいして教えることもなく、最初からヒョイヒョイやってくれて、数字も挙げてくれてっから、非常に助かります。あとは彼の見えない努力も当然あると思います。

翔平 僕は営業に入った当時はコロナ禍ですぐに出張等にも行けず、お互いの顔を知らない中でも営業活動をするのは大変でした。だから休みの日に遊びに行ったついでに、お客さんのところにも顔を出していました。お客さんからは、『月イチで来るヤツいねえぞ、もう来んな』って言われます(笑)。
■海が好き
翔平さんは広島県出身の現在28歳。東海大学海洋学部海洋文明学科卒。その彼が、どうして気仙沼にやってきたのでしょうか?
翔平 たまたま大学に東北地方のインターンシップの募集が来ていて、その中に“氷の水族館”もあり面白そうだと思ったので参加。大学4年の時は岡本製氷さんでバイトをしながら、卒論を書いていました。
2019年4月に住民の半世紀来の悲願だった「気仙沼大島大橋(愛称「鶴亀大橋」)」が開通しましが、翔平さんは卒論で“大島に橋ができることによる効果と予測”をまとめました。鶴亀大橋は本島と大島を繋いだだけでなく、翔平さんと気仙沼とを繋ぎました。
翔平 インターン仲間に同級生が多かったので、そこで別のヤツがインターンしてる会社の社長さんとの輪も広がっていきました。当時は何をやりたいのか決まってなかったので、いろんな職種で内定ももらったけど、その中でせっかく水産をやってきたからと足利本店さんに決めました。もし合わなかったら、地元に帰ればいいやと(笑)。
育美 そうだったんだ。たまたま……。大島の橋が架かるタイミングで、しかも岡本製氷さんにインターンって……。それが今では、めっちゃ水産に関わる仕事を任されて、すごい!
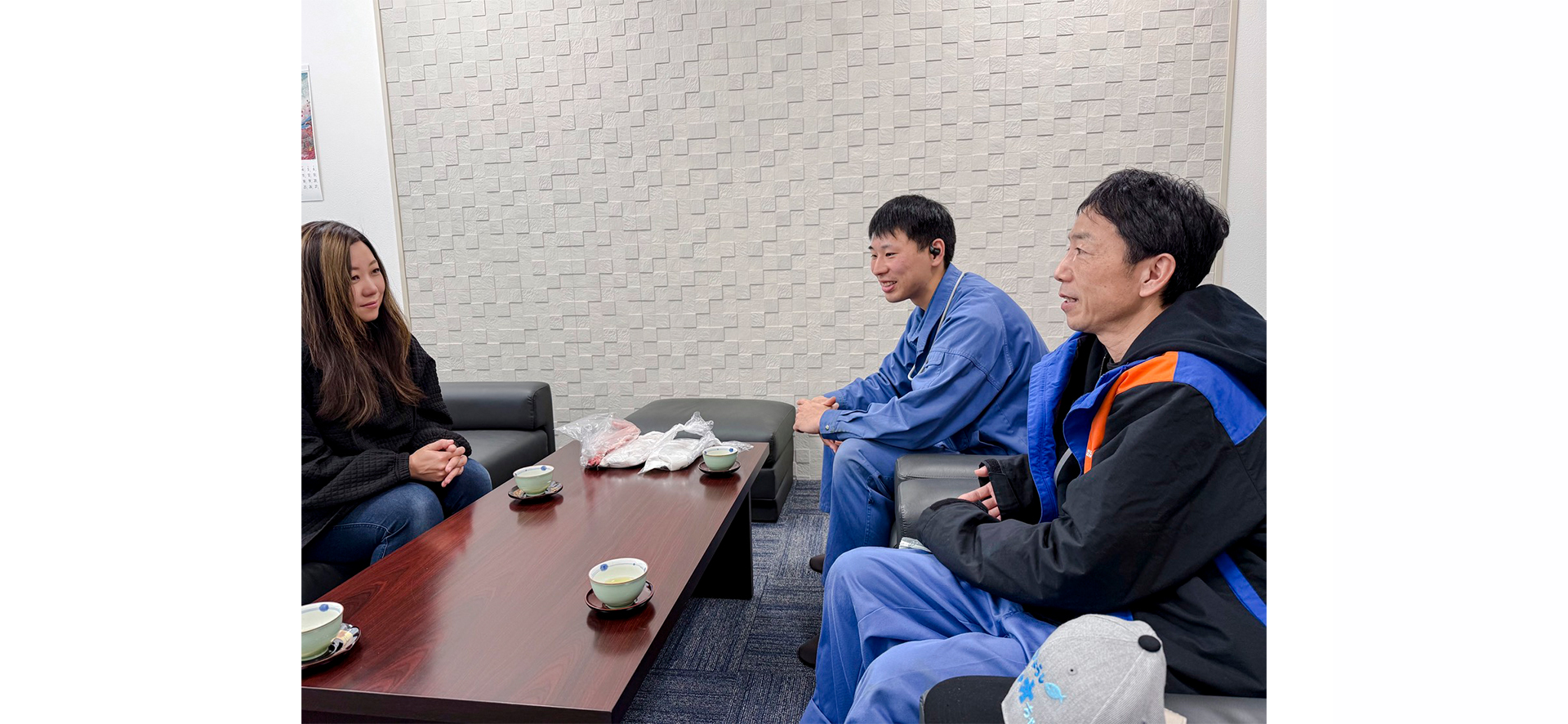
翔平 初心者マークがあるうちに恐れずに、怒られるのを覚悟でやらかしまくって、お客さんに怒られて「もういらない」って言われつつ、それでも「じゃ、また明日電話しまーす」って、ガツガツいってました。
魚がなくても、雑談の電話してましたね。1年目でお客さんとの関係値を作り、私が担当している全国25箇所でお客さんも若い人が増えてきました。その中で、ベテランは片手で数えるほどですが、やっぱり困った時に頼りになるのはベテランの方です。
小松 海は予想がつかない。完全に他力なんですよ、我々。だから一本釣りの船頭さんなどいろんな人と友達になって、市場で積極的に話しかけたり、飲みに行ったり情報を集めるのも大事です。
育美 翔平さんも、堂々と目上の人ともやりとりされていて、すごいなと思いました。翔平さんはどんな時に、やりがいや達成感を感じますか?
翔平 大きな夢や目標はないけど、自分が気にいった魚に対して、お客さんの評価が良かった時はうれしいですね。たとえば、『連休明けで売れなかったけど、魚は良かった。また、似たようなのお願い』って……』。やっぱ魚がよかったって言われると、次も頑張ろうと思う。逆に、自分では良いと思っていたけど悪い評価の時には、お客さんとの目線がずれてるから合わせなきゃいけない。
育美 魚を買うという仕事の裏側。貴重なお仕事の現場に、潜入させていただきました。お取引の一つひとつには、人と人との信頼関係が積み重なっていることを実感。
海の状況は、誰にも読めない。だからこそ、人を知り、魚を知り、現場に立ち続ける。とても、かっこいいお仕事です。

魚市場でも会社内でもイキイキと働く翔平さん。気に入らなかったら地元に帰ればいいやと飛び込んだ、買受人という特殊な営業職。今では朝型の生活リズムも染み付き、すっかり逞しい買受人の顔です。
※1:『気仙沼と水産 令和7年版』(発行:気仙沼市)参照。会社によって複数人所属。
(取材日:2025年11月27日)
構成・文・撮影/藤川典良
- 2026-01-30 海が教えてくれる Vol.10 〜 足利本店 〜
- 2026-01-14 海が教えてくれる Vol.9〜漁師居酒屋〜
- 2025-12-04 海が教えてくれる vol.8 〜岡本製氷冷凍工場〜
- 2025-09-23 海が教えてくれる vol.7 〜藤田製凾店〜
- 2025-09-01 海が教えてくれる vol.6
〜津波による牡蠣養殖被害の現場から〜 - 2025-08-18 海が教えてくれるvol.5 〜気仙沼市魚市場〜
- 2025-08-01 海が教えてくれるvol.4 〜宮城県北部船主協会〜
- 2025-07-01 海が教えてくれるvol.3
〜かつお溜め釣り漁伝来350年 阿部長商店 〜 - 2025-06-24 海が教えてくれる vol.2
〜気仙沼かつお溜め釣り漁伝来350年 小野健商店〜 - 2025-06-17 海が教えてくれる vol.1 〜気仙沼つばき会〜
- 2025-05-02 海が教えてくれる
- 2024-11-19 親と子の思い出をつくる<ニューボーンフォト>
- 2024-09-02 人を旅する
〜気仙沼はいつでも待っていてくれる場所〜 - 2024-08-14 私のKESENNUMA SONGS
シンガー FRAM × 熊谷育美 - 2024-03-03 居心地のいい空間 vol.2
- 2024-03-03 居心地のいい空間 vol.1
- 2023-11-05 子どもを思う、家族を思う
〜「家族の週間」で、日々を振り返る〜 - 2023-09-18 ピアノが繋いだ『絆コンサート』佐賀 富士にて
- 2023-08-07 にじむ、まじわる
うみ、そら、ひと
〜水が彩る情景 山本重也さんと気仙沼 vol.2〜 - 2023-07-31 にじむ、まじわる
うみ、そら、ひと
〜水が彩る情景 山本重也さんと気仙沼 vol.1〜 - 2023-05-26 2023 初夏の気仙沼
- 2022-12-23 木と暮らす〜港町で育む、木工品のぬくもり〜
- 2022-12-09 音楽を描く 〜移住1年、ものづくりを楽しむ〜
- 2022-09-23 坂本サトル ⇄ 熊谷育美 【音楽的 往復書簡】
- 2022-07-09 音楽とデザイン 〜音を観る、アートワークで聴く〜
- 2022-06-29 「気仙沼とわたし」2022年夏〜満喫、気仙沼〜
- 2022-06-15 音楽のUbgoe vol.2 〜楽曲制作と新曲に込めた思い〜
- 2022-05-18 音楽のUbgoe vol.1 〜ボーカル録音と二人の出会い〜
- 2022-02-16 「気仙沼とわたし」2022年 2月・冬~生わかめ・生めかぶ編~
- 2022-01-18 命を獲る漁師、空気を撮る写真家
- 2021-12-13 <Ubgoe>が、産声を上げる瞬間
- 2021-11-29 「気仙沼とわたし」 2021年11月・秋~デビュー12周年編~