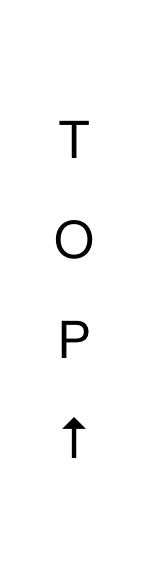Kesennuma

港に並ぶ白い漁船が青い海と空の中で映え、陽の光を浴びて輝く季節がやってきました。
「海と生きる」港町・気仙沼で生まれ育ち、今も私は毎日この港を見て、今日は何が水揚げされたのかなって気になってしまいます。
私自身、海産物は大好物ですが、実は私の家系を見ていくと水産は身近な存在なんです。
父方の祖父は三人兄弟で、みんな水産業に関わっています。
私の祖父のお兄さんはワカメなどの生産・加工会社を、弟さんは鰹節製造会社を経営しています。
(今はそれぞれ息子さんたちの代に継がれています。私の父の従兄弟にあたります。)
鰹節の伝統的な製法は日本でも非常に珍しくて、伝承している人は日本に数人なんですって。
そして私の祖父はその昔、漁船に乗っていたんだとか。
水産高校の学生が乗る実習船<宮城丸>にも、乗っていたことがあるそうです。

水産業に関わる親戚もいたので、昔からお魚やウニなどを親戚からたくさんいただいていました。
そんなこともあり、我が家にも冷蔵庫のほかに保存用の冷凍庫がいくつかあります。
お魚もまるごといただくので、祖母が捌いているのをよく見ていました。
デビュー後も変わらず気仙沼に暮らしてきた私は、幼少の頃から見てきたごくごく自然な気仙沼の情景を楽曲で描いてきました。
出船送りをする女性の姿や、家庭を守る女性の姿もそうです。
しかし例えば、魚が水揚げされるところや競りの様子、冬の風物詩である「気嵐(けあらし)」などは、観光客の皆さんの方が詳しいかもしれませんね。
私は早起きが苦手ということもありつつ、日常すぎて自分から見学しに行くことはほとんどしてこなかったなと思います。
遠方からの来客に案内する時くらいでしょうか。
気仙沼には、まだ真っ暗な早朝の時間からお仕事されている方がたくさんいらっしゃるんですよね。
子どもたちも成長し、きょうだい三人ともお魚が大好き。一番下の娘は、お魚図鑑をよく見ています。
お魚のこと、港のこと、水産業のこと、いろいろと知らないことも多いなと改めて思う日々です。
漁業のこと、魚市場の様子、新しく漁師になられた移住者の方のお話しなどなど、気仙沼で暮らしていながら知らなかったことはたくさんありそうです。
そうそう今年は、かつおの溜め釣り漁が気仙沼に伝来して350年だとか、色々話題も豊富です。
来年2026年3月で、東日本大震災から15年。
気仙沼の風景もですが、地元のみなさんもこの15年で様々な変化があったかと思います。
そんな「海と生きる」港町・気仙沼の水産業を、私自身が改めて海に関わる人たちに学び、折に触れ『気仙沼とわたし』でみなさんにもお伝えしていきたいなと思っています。
もちろん音楽の話題もお届けしますので、楽しみにしてください!
構成:藤川典良