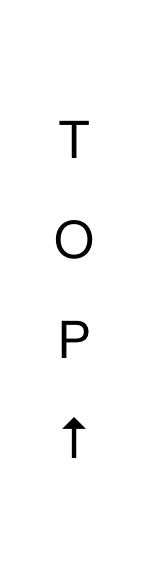Kesennuma
〜津波による牡蠣養殖被害の現場から〜

2025年7月30日 午前8時24分(日本時間)、ロシアのカムチャツカ半島付近でマグニチュード8.7の地震が発生(後に8.8に修正)。この地震で発生した津波の影響で、気仙沼市では牡蠣養殖業者を中心に、養殖筏(いかだ)の損壊など大きな被害が出ました。特に被害の大きかった気仙沼大島亀山地区で牡蠣養殖業を営むヤマヨ水産の小松武さんに、津波発生時の様子や被害状況など、お聞きしました。
■なすすべなく壊れる養殖筏
気仙沼湾内に位置する気仙沼大島は東北最大の有人島。本島側の気仙沼の鶴が浦と大島の亀山との海峡・大島瀬戸は、大川の栄養豊富な水が流れ込む汽水域のため牡蠣の身入りも良くなり、特に内湾寄りは絶好の養殖漁場です。
地震の影響で、8時37分には日本の太平洋沿岸の広範囲で津波注意報が発令され、この段階で予想された津波の高さは宮城県沿岸で1m。その後、9時40分には津波警報に切り替わり、津波の高さも3mに修正。
「カメラの映像を見ていたら、ロープが1本切れて筏が動き始めたのを合図に、筏が打つかり合い重なって壊れていきました。じわじわと目の前でなすすべなくやられているのを、ただ見ているしかありませんでしたね。およそ30分間隔で押し寄せてくる上げ潮と引いていく下げ潮に明らかに切り替わって、まるで川のように浮遊物が流れていたんです。今まで壊れてなかった筏が壊れて、組んでいた竹が立ち上がっていく。暗くなるとぶつかりあったり、ロープが切れたりする音が不気味に響いていました。気仙沼は確か99センチの津波(気仙沼漁港 最大値13:54)でしたが、自然の力は容赦がありません」
30日20時に津波注意報に切替わり、その注意報が解除されたのは翌31日16時30分でした。
■難易度の高いところから復旧
いつも気仙沼大島大橋(鶴亀大橋)」橋上から大島瀬戸を眺めると、たくさんの筏が整然と並んでいるのが見えていました。それが今は、津波の影響で乱れています。

「筏の間隔は船を横付けして水揚げしたりできるように空けていますが、今は、縦になったり横になったり……。くっついたままじっと動かずにあり続けるっていうのは、海底と繋がっているアンカーロープが大きく捻じれて絡まっていて、それがある意味新しいアンカーロープのようになって、強い風ででもガチッと動かないような状態になっています。いつもは風でなびくんですけど、柔軟性がなくなっていますね」
カムチャツカ半島地震による津波は太平洋沿岸の広範囲に及びましたが、被害の大きかったのは気仙沼大島の亀山地区、外浜地区、唐桑半島などの沿岸部。ほかの地方では、三重県でも被害が大きかったようです。

「正直、復旧するのは、津波でリセットされるよりも厄介なんですよ。骨でも、骨折よりもヒビの方が治りにくいと言いますが、まさにその状態です。水中で絡み合った牡蠣が付いたロープをほぐしながら一つひとつ筏を引き離したり、元の場所に戻すまでの間に仮置き場所を作ったりする復旧作業が必要になります。
被害の大きかった漁場は、抜群に牡蠣の生育が良いところなんです。奥側の潮の穏やかなころは後回しにしたとしても、潮通りのいい、牡蠣の成長の良いところからと、難しいけど本能的にそこから普及しはじめています」

自然は読みきれません。昨年は、海水温が高くだらだらと牡蠣の放卵が続き、温湯処理(※3)した上にさらに牡蠣の卵がびっしりつき、自分で採苗してタネから製品化する挑戦もできるかもと考えたほどで散々だったと小松さんは1年前を振り返ります。
しかし今年は猛暑日が続き、地上は茹だるような暑さだというのに、大島瀬戸では海水温は昨年よりも3、4度低く、海の中は改善してそうです。
「昨年は磯焼けして海藻がなかったところも今年は繁茂していて、生き物には快適なはず。だから、牡蠣の生育もすごく期待できる年だったんですが、そこにこの津波です。それでも残ったやつはいいんじゃないかな。今が産卵の真っ最中なので、筏が壊れて海中に沈んでる部分も引き上げて見ると、もう今年の赤ちゃんたちが小指の爪の半分ぐらいの生まれたって分かるようになっているんです」
今回、ロシア側からの津波の影響が如実に出ていたことがあると小松さん。
「海水が入れ替わって、3日、4日間ぐらいは海水温が2度ほど低かったんです。24度ぐらいの時期の津波だったのが、22度まで……。北から津波が来たんだって、わかりやすく海水温が下がっていました。津波もおさまって作業をやる頃には、また24度ぐらいに戻っていましたが……。だから、自然にいいように遊ばれている感じは否めないです。人間の力は微力すぎて、無力に近いぐらいです。けれど復旧すれば、今年の冬から来年の春にかけて残った牡蠣はいいものが出来ると思います」
■助け合いの、手
津波被害から1ヶ月。現在は朝5時前に同じ浜の牡蠣養殖の仲間と共同作業で、その場の状況を相談しながら復旧作業を進めています。
「筏を固定するためのアンカーは砂利を袋詰めした物を使いますが、その作業は牡蠣の冬季出荷が始まるまで時間がないことから今回は初めて外注しました。亀山地区までの道幅は狭く、それを運んできてくれる10tダンプは通れないため、荷下ろし場所として使わせていただきたいと対岸の浜の同業者の大先輩にお願いしたところ二つ返事でお許しいただきました。
2年前に、『手広くやってるわけでもなくなったし、お前たちやる気があんだったら使え』っていう感じで養殖の場所も使わせてもらっています。さらにフォークリフト使っていいだとか、スイカを差し入れてもらったり、本当に良くしていただいています。自分たちがそういう世代になった時に、今度は私たちが同じように、後輩たちにできたらなあって思いますね。本当に、尊敬します」

「まだ暗いうちに水揚げするので、あるべきところに筏が並んでないと座礁してしまいます。だから、9月中下旬までに筏を並べ直すのが今の目標ですね。そして、残っているすべての牡蠣を温湯処理ができたら理想です。春になったら生き物のサイクルとして身入りがよくなるのは当たり前なんですけど、少しでも良いものを収穫しようとするとやっぱり温湯処理はした方がいいですよ。9月末までに形を整えて、10月の3週間ぐらいでなんとかできるだけ今年収穫する分を温湯することができたら100点ですね」
ヤマヨ水産では4割強の筏が津波の被害にあいました。完全復旧には莫大な費用と時間を要しますが、水面下では残った牡蠣が今も確実に育っています。気仙沼市では、いち早く牡蠣養殖のための支援を開始しました。
「正直、気仙沼市がすぐに、牡蠣養殖支援のためのクラウドファンディングの形を整えていただけたスピード感がすごく嬉しいですね。今回、気仙沼市のこの取り組みに希望を見させてもらえました。もちろん皆さんのご支援やお声も本当にありがたいですし、このタイミングで瞬発力を発揮してやってもらったっていうのだけで、充分踏ん張りが効くと思っています!」
日本以外で発生した地震で津波注意報が発令されたのは、2010年2月の南米チリで発生した地震(M8.8)以来。翌年(2011)年には、東日本大震災。地震に限らず、台風、大雨など、自然災害は毎年どこかで相応の爪痕を残しています。
「なんでこんなに大変なのに、読めない自然相手の漁師をやるの?って、思う人はいるでしょうね。定期的に、確実に自然災害にやられるのが折り込まれてい流のにって。でも日頃の行いが悪いと自分を責める必要もないし、仕方がないんだから、育ってくれる牡蠣を相手に、できたものを『美味しい!』と喜んで食べてもらえるんだから、いい仕事だなって思うんですよ」
沈んでしまったり、流れてしまった筏もある。けれど、壊れた筏の下に残る牡蠣を活かしながらの復旧作業は、経験値があっても思うようにいかず、試行錯誤の繰り返し。気仙沼牡蠣養殖漁師の復旧作業は、続きます。
熊谷育美 より
「津波の被害の大きさが生々しく伝わってきました。
復旧は想像以上に厳しく、漁師の方々が背負う苦労を思うと胸が痛みます。
それでも、牡蠣を大切に育てる姿、海への深い愛情、地域のみなさんとの固い絆。
今回のインタビューには、学ぶことが数えきれないほど詰まっていました。
自然災害への危機感も新たに身の引き締まる思いです。
海と生きる、気仙沼。
どうかみなさま、これからもいっしょに応援してまいりましょう」
※1気仙沼市デジタル水産業推進協議会:令和5年8月、水産庁が全国から公募する「デジタル水産業戦略拠点」に気仙沼市が選定されました。ヤマヨ水産の小松武さんは、本協議会の委員も務めています。本記内で紹介した動画は、もともと協議会が大島瀬戸と養殖場の状況を記録するために設置されたカメラでしたが、津波の襲来状況を捉えた貴重な映像となりました。
※2 垂下式:牡蠣養殖は、ホタテガイの殻に牡蠣の赤ちゃん(幼生)を付着させたものを一つのロープにいくつもつけて(垂下連)、これを筏から海中に吊るして牡蠣を育成・収穫します。
※3 温湯(おんとう)処理:筏に吊るした牡蠣を、船の上で75度のお湯に一定時間つけて、牡蠣殻に付着したシュウリ貝や海藻類など牡蠣以外のものを死滅させる手法。温湯処理をすることで付着物を取り、牡蠣より先にプランクトンを食べてしまうのを防ぎます。そうすることで、牡蠣がぷっくり大きく育ちます。
(取材日:2025年8月21日)
協力/気仙沼市産業部水産課
写真提供/ヤマヨ水産
構成・文/藤川典良
■気仙沼市 カムチャツカ半島地震による津波被害で支援開始■
気仙沼市では被害を受けた市内のカキ養殖業者等を支援するため、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。
受付期間は、令和7年9月30日まで。
詳細は、こちら